有機農業とは?無農薬栽培との違いやメリット・デメリットを解説

有機農業は、農作物本来の成長速度で育てる農業形態です。 化学肥料や農薬に頼らない有機農業は、環境の負担が少なく、土壌周辺の生態系に悪影響を与えません。 ただし、農作物の育成や収穫には手間がかかります。この記事では、有機農業の概要や、他の栽培方法の違いなどを解説します。 有機肥料のメリット・デメリット、種類なども記載してあるのでぜひ参考にしてください。
- 目次 -
有機農業とは
有機農業とは、化学肥料や農薬に頼らない農業形態のことです。 別名で「オーガニック」や「有機栽培」などと呼ばれています。 「有機農業の推進に関する法律」における、有機農業の定義は以下のとおりです。
・化学的に合成された肥料及び農薬を使用しない
・遺伝子組換え技術を利用しない
・農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減する
有機農業は、化学肥料や農薬に頼らず、自然と共生しながら農作物を栽培できます。
※参考:有機農業とは – 農林水産省
有機農業と他の栽培方法の違い

農業は、農薬の使用の有無によって栽培方法が異なります。ここでは、有機農業と他の栽培方法の違いについて解説します。
無農薬農業
無農薬農業とは、農薬をまったく使用しない農業形態です。 ただし、「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」などの表記は、優良誤認されるため禁止されています。
有機農業は、認可された農薬を使用して農作物を栽培する方法です。 各地方の公共団体が農薬の基準を定めており、農薬の使用回数が基準の50%以下、化学肥料の使用量50%以下のものを「特別栽培」と呼びます。
慣行栽培
慣行栽培は、化学肥料や農薬を使用する栽培方法です。 別名「従来型」とも呼ばれ、国内の農作物を生産する方法で最も利用されています。慣行栽培は収穫量を確保でき、農作物の形が整います。 また、天候にも左右されにくく、農作物を市場に安定して集荷することが可能です。ただし、土壌が化学肥料や農薬の使用によって有機質を失い、やせ細ります。
農産物の安全性はどう判断する?

農産物の安全性は「有機JAS認証」「グローバルGAP」によって判断できます。ここでは、それぞれについて解説します。
有機JAS認証
有機JAS認証とは、農林水産省が有機農業の農産物に定めた基準です。 有機JAS認証を受けた農産物のみが、有機野菜としての販売が認められます。 ただし、有機JAS認証を取得するのは困難で、大きく分けて以下2つの原則を満たす必要があります。
1.有機JASの生産基準を満たすほ場や栽培場、加工場などの所有
2.有機JASの定める生産管理や生産管理記録の作成
グローバルGAP
グローバルGAPは、農産物の安全性を国際的に証明するものです。 農産物の安全性や労働環境などを含めて、第3者による生産現場のチェック項目を満たす必要があります。
また、グローバルGAPは、持続的な生産活動を行う企業に対する認証でもあります。 持続的な生産活動とは、農業生産の環境や社会などに配慮した活動のことです。
有機農業のメリット

有機農業は、農作物や栽培する環境など、さまざまなメリットがあります。ここでは、有機農業のメリットを解説します。
野菜本来の味を楽しめる
有機野菜は味が濃く、うまみを強く感じられる点が特徴です。 有機農業は土の中にある有機物の力を利用し、植物本来の成長速度で育てるためです。 また、農作物のえぐみが少なくなるので、栄養豊富な皮ごと食べられます。化学肥料や農薬を使用して成長した農作物は、野菜本来の味や風味が落ちます。
環境にやさしい
有機農業は化学肥料を使用した栽培方法と異なり、土壌の有機質を残します。 化学肥料を使用した農業は有機物を減らし、土壌周辺の生態に悪影響を与えます。 土壌の有機物が減ることで、微生物や虫、動物などの減少につながるためです。 有機農業は環境汚染を抑えて農作物を育てられるため、環境に配慮した農業を行えます。
消費者から注目されやすくなる
有機農業で育てられた農作物は、消費者に安全性をアピールしやすくなります。 ほとんどの農家は慣行栽培を行っており、容易に差別化ができるためです。 有機野菜は、食の安全性にこだわる人の興味を引きます。 有機農業の農作物は、有機野菜を使用したレストランや小売店などに販売できるでしょう。
有機農業のデメリット

有機農業は農作物を育てる手間が増えて、販路が少ない特徴があります。ここでは、有機農業のデメリットを解説します。
収穫量が少なくなる
有機農業は、慣行栽培に比べると成長速度が遅い傾向にあります。 化学肥料や薬品を使用しない農業を行うと、農作物が本来の成長速度で育つためです。 有機農業は慣行農業に比べて収穫量が少なく、計画的な生産も不向きといえます。ただし、農作物の単価を上げると、農業の収入を上げやすくなります。
雑草や病害虫の対策が必要になる
有機農業は除草を手作業で行ったり、害虫を駆除したりする必要があります。 有機農業で使用できる薬品には、限界があるためです。 慣行栽培のように化学肥料や薬品に頼らないため、有機野菜の栽培には人手や時間がかかります。 有機農業は栽培の技術が確立されておらず、有効なノウハウを実施することは困難といえます。
販路が限定される
有機食品の流通・加工業者は、少ない傾向にあります。有機野菜は収穫量が少なく、販路が拡大しにくいためです。 農産物の販路は直接販売が多く、有機野菜は一般に流通する野菜よりも販売価格が高めになります。 有機野菜の需要に対して、供給が追いついていないことも、販路が少ない要因です。
有機肥料の種類

有機肥料には、さまざまな種類があります。ここでは、有機栽培に使用する肥料を5つ解説します。
油粕
油粕(あぶらかす)は、ナタネやダイズなどの種から油を搾り取ったものです。 油粕には窒素が多く含まれており、作物の葉や茎の生育を促す効果があります。 農作物の作付け2〜3週間前には、土に油粕をよく混ぜておきましょう。 ただし、油粕を多量に使用するとガスを発生させたり、小バエを発生させたりする原因になります。
鶏糞
鶏糞(けいふん)とは、ニワトリの糞を発酵させたものです。 鶏糞は格安で手に入るうえに、化学肥料と同じように速効性があります。 農作物の作付け1週間程度前に鶏糞を土に混ぜておきます。ただし、鶏糞を過剰にまくと、土のアルカリ性が強くなってしまうため注意しましょう。 土作りをする際に、石灰資材を混ぜる必要性はほとんどありません。
魚粉
魚粉(ぎょふん)は魚を乾燥させて、水分と脂を抜いて粉末にしたものです。 魚粉を使うと、果菜や葉菜などの味をよくする効果を期待できます。 魚粉は土中で速やかに分解し、窒素の即効性が高い点が特徴です。 作付け2週間程度前には、魚粉を土に混ぜておきましょう。 土の表面に散布して放置すると、鳥や虫に食べられてしまうので注意が必要です。
米ぬか
米ぬかは、精米した後の米から出る粉です。米ぬかには糖分やタンパク質などが多く含まれているため、土壌の微生物を活発化させる効果を期待できます。作付け2週間前に米ぬかを散布し、土によく混ぜて使用しましょう。 米ぬかは虫のエサになったり、産卵場所になったりする点に注意が必要です。
草木灰
草木灰(そうもくばい)は、草木を燃やした後に残る灰です。 草木灰の成分はアルカリ性であるため、酸性の土壌を中和できます。 草木灰はカリを多く含むので、油粕や魚粉などの成分を補う目的で使用されます。 作付け1週間前には、土に草木灰を混ぜておきましょう。 ただし、草木灰には窒素がほとんど含まれないので、油粕のような肥料と併用して不足分を補います。
まとめ

有機農業は、化学肥料や肥料に頼らない農業形態です。 有機農業で育った農作物は、自然本来のうまみを感じられます。ただし、有機野菜は収穫量が少なく、雑草や病害虫の対策が必要です。 販売する際は、「有機JAS認証」「グローバルGAP」などの認証を受ける必要があります。
プラスワイズは、農業資材や農業用品、農機具を扱うオンラインショップです。約3万点の商品を提供しており、 園芸薬剤や用土・肥料、運搬機器なども含め、幅広いアイテムを取り扱っています。農業資材・農業用品をお買い求めの際は、ぜひプラスワイズをご利用ください。
農業用品ネットで買うならプラスワイズ! 3万点以上の商品を全国へお届け!
前身である中川商店(1967年創業)から続く取引先との信頼も厚く、幅広い農業知識と便利な農業用品を、ネットを通して新潟県からお届けしております。



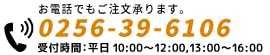


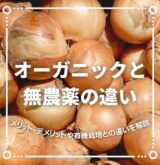




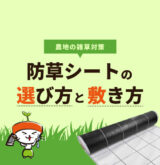














































































































































































































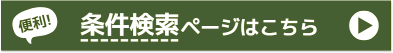
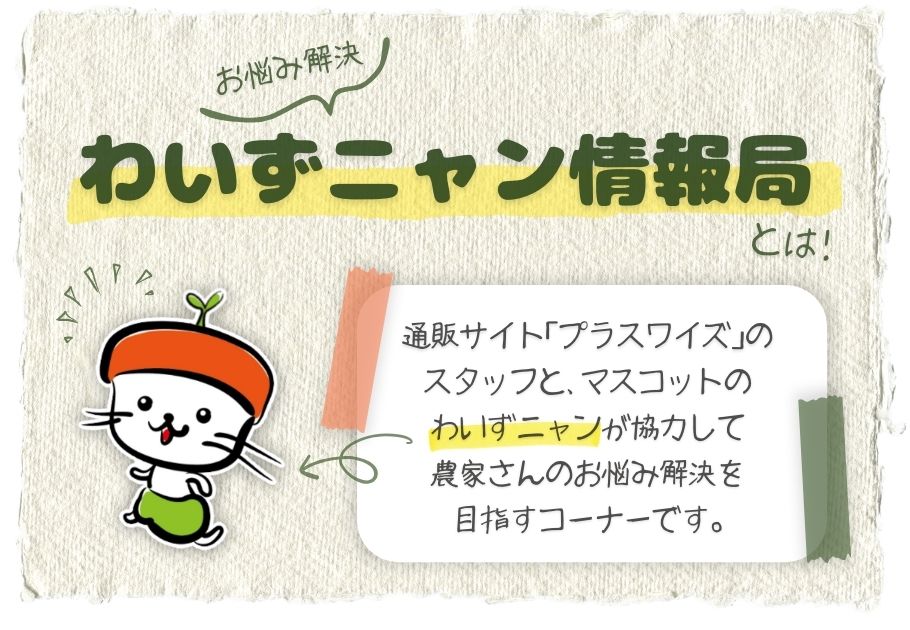









 お届けについて
お届けについて